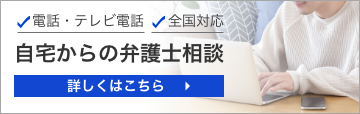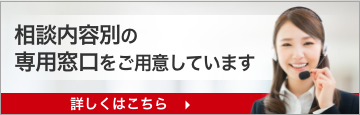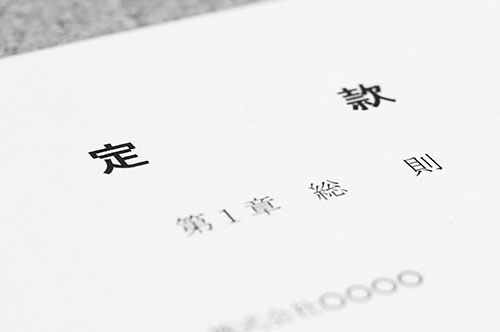退職勧奨で言ってはいけないこと|よくある例や注意点について
- 労働問題
- 退職勧奨
- 言ってはいけないこと

従業員を解雇するには、厳格な要件を満たさなければならないため、簡単には解雇することができません。そこで、辞めてもらいたい従業員がいる場合に用いられるのが「退職勧奨」という方法です。
退職勧奨は、従業員に退職を促して、自ら退職してもらう方法ですので、解雇のような厳格な規制は及びません。しかし、退職勧奨の態様や方法によっては、違法な退職強要にあたる可能性もありますので、従業員への伝え方には特に注意が必要になります。
今回は、退職勧奨で言ってはいけないことや、違法な退職勧奨をしてしまったときのリスクなどについて、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、そもそも退職勧奨とは
そもそも退職勧奨とはどのようなものなのでしょうか。以下では、退職勧奨の概要と簡単な手続きの手順について説明します。
-
(1)退職勧奨の概要
退職勧奨とは、企業が従業員に対して退職を促すことをいいます。退職するかどうかは、従業員の意思に委ねられていますので、強制力はありません。解雇のように厳格な法規制がないので、辞めさせたい従業員がいる場合において、解雇に代わる手段として利用されています。
ただし、従業員に退職を促すにとどまらず、退職を強要するような言動などがあると、違法な退職強要となり、違法になる可能性もありますので注意が必要です。 -
(2)退職勧奨と解雇との違い
退職勧奨と解雇は、いずれも従業員を辞めさせる手段として利用されますが、両者は、強制力の有無という点で異なります。
解雇は、会社側の一方的な意思表示により労働者との雇用契約を解消することができますので、退職勧奨とは異なり強制力のある処分です。
解雇は、労働者に対して重大な不利益を生じさせる処分であることから、厳格な要件のもとでのみ認められています。 -
(3)退職勧奨の手順
従業員に対して退職勧奨する場合には、明確な方針を定め、従業員との面談を通して退職届を提出してもらう、といった手順を踏みます。簡単にご紹介しましょう。
- ① 退職勧奨の方針決定
まず、どのような理由で退職勧奨をするのかを明確にしておきます。労働者から質問や反論があったときにすぐに対応できるよう、担当者間で退職勧奨の方針を共有しておくことも大切です。
- ② 従業員との面談
退職勧奨は、従業員を個室に呼び出して面談形式で行うのが一般的です。
従業員から退職を強要された、などと言われないようにするためにも、伝え方はもちろんのこと、面談時間や回数、会社側から出席する人数などについても、十分に配慮するようにしましょう。
たとえば、窮屈な部屋に会社側から複数人が入って面談をしたり、長時間話をしたりすると、従業員から不当な圧力と思われてしまうかもしれません。また業務時間外の面談も、状況によっては面談自体を強要された、と捉えられてしまうおそれがあるので、注意しましょう。
- ③ 退職届の提出・退職合意書の作成
面談などを通じて、従業員が退職の意思を示したときは、従業員から退職届を提出してもらいます。
退職勧奨に応じて退職したことや、退職条件を明確にするためには、退職合意書を作成するのも有効な手段です。
退職合意書とは、退職条件や退職後の約束などを記載した書面を指します。合意書を締結することで、口約束よりもトラブルを予防しやすくなります。
- ① 退職勧奨の方針決定
2、退職勧奨で言ってはいけないこと|よくある例
退職勧奨では、従業員に対して言ってはいけないことがあります。以下のような発言をすると、退職強要と言われる可能性がありますので、注意が必要です。
-
(1)従業員を罵倒・侮辱するなどの人格を否定するような発言
従業員を罵倒・侮辱するなどの人格を否定するような発言をして退職を促すと、違法な退職強要と評価される可能性があります。このような発言により従業員が精神的苦痛を受けると、不法行為として慰謝料を請求される可能性もあります。
罵倒・侮辱など、人格を否定するような発言例としては、以下のようなものが挙げられます。(例)- お前みたいな役に立たない人間は辞めてしまえ
- あなたは会社のお荷物だ
- 給料泥棒
- みんなお前に辞めてもらいたいと思っている
退職勧奨の際に、従業員の能力不足や勤務態度などを指摘することもあるでしょう。しかし、指摘がエスカレートして従業員の人格を否定するような発言にならないよう、注意が必要です。
-
(2)退職勧奨以外に選択肢がないかのような発言
会社から退職勧奨に応じる以外に選択肢がないかのような発言をすると、事実上、退職を強要したといえますので、違法な退職強要にあたる可能性があり、またもし解雇と評価された場合には労働契約法上、使用者は大分不利な立場になります。
たとえば、以下のような発言が挙げられます。(例)- 退職勧奨に応じなければ解雇する
- 退職勧奨に応じなければ面談は終わらない
- 会社に残ったとしてもお前に居場所はない
-
(3)退職勧奨に応じないと不利益を与える旨の発言
退職勧奨に応じないことを理由に、従業員へ減給などの不利益を課すことも、違法な退職強要とされるおそれがあります。事実上、従業員に対して、退職勧奨に応じる以外に選択肢がない状況にしているからです。
このケースで言ってはいけないこととしては、以下のような発言が挙げられます。(例)- 退職勧奨に応じないと遠方のオフィスに移動させる
- 会社に残ったとしてもこれ以上の昇進は見込めない
- 退職勧奨に応じないなら減給する
-
(4)解雇相当でも、退職勧奨で任意の退職を促せる
従業員への対応として普通解雇や懲戒解雇が相当な場合でも、まずは任意の退職を促すために退職勧奨が利用されることもあります。
従業員を解雇する前に退職勧奨を行う場合は、面談時に「退職勧奨に応じない場合、普通解雇や懲戒解雇を予定している」などと従業員に伝えることは違法にはなりません。
ただ、従業員に解雇を予定している旨を伝えても退職勧奨に応じてもらえず、解雇に踏み込まざるを得ない場合もあるでしょう。その場合は、「退職勧奨に応じなかったから」ではなく、解雇相当とみなした従業員の言動など、もともとの解雇理由を伝えるようにしましょう。
3、退職勧奨が違法となった場合に会社側が負うリスク
従業員の人格否定、退職勧奨以外の選択肢を与えないような発言をするといった違法な退職勧奨をしてしまうと、会社側には、以下のようなリスクが生じます。
-
(1)従業員に退職してもらえない
違法な退職勧奨は従業員の反発を招き、退職に応じてくれない可能性が高まります。その結果、問題のある社員が会社に残ってしまうこともあるでしょう。
退職勧奨に応じないことを理由に、減給や配置転換など、従業員に不利益を与えることも違法ですので、状況を変えられないおそれがあります。 -
(2)紛争に発展する可能性がある
違法な退職勧奨を行い、それが退職強要と評価される場合には、従業員から退職の無効を理由として訴訟を提起される可能性もあります。
訴訟を提起されてしまうと、それに対応するために社内の貴重なリソースを割かなければならず、業務に支障が生じるリスクが生じます。また、訴訟で会社側が敗訴し、それが万が一世間に広まってしまうと、悪質な企業とのレッテルを貼られてしまい、企業の社会的信用性が大きく低下してしまうこともあるでしょう。 -
(3)金銭を支払わなければならない可能性がある
先述のとおり、たとえ従業員が退職したとしても、後から違法な退職勧奨があったと訴訟される場合があります。実際に退職勧奨が違法と判断されたり、解雇があった上で無効だったと評価されたりすると、慰謝料や賃金など金銭の支払を要することになります。
4、退職勧奨に応じない従業員を辞めさせるには?
退職勧奨に応じない従業員を辞めさせるにはどうしたらよいのでしょうか。以下では、具体的な対処法を説明します。
-
(1)退職条件の上乗せを検討する
退職金などの退職条件が希望に満たないといった理由で、従業員が退職勧奨に応じない場合は、退職条件の上乗せを検討しましょう。退職金の上乗せをする場合、会社としては経済的な負担となりますが、長期の視点で考えれば、問題のある従業員を残すよりもメリットになる場合もあります。
なお、従業員が退職勧奨に応じない意思を示した後であっても、退職条件の上乗せをして、再度退職勧奨をすることは違法ではありません。従業員の態度や拒否する理由を見極めながら対応していくとよいでしょう。 -
(2)解雇を検討する
従業員に解雇事由がある場合には、退職勧奨ではなく解雇により、辞めさせることが可能です。ただし、従業員を解雇する場合には、厳格な要件を満たさなければならず、安易な解雇は不当解雇になるリスクがありますので注意が必要です。
解雇が可能なケースであるかどうかを判断するためには、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談をすれば、解雇の可否はもちろん、手続きについてもアドバイスを受けることができます。また、万が一不当解雇で訴えられたとしても、適切に対応してもらうことが可能です。
5、まとめ
退職勧奨では、人格否定などの言ってはいけないことがあります。面談がヒートアップするなどして、つい、言ってはいけないことまで言及すると、違法な退職勧奨と評価され、退職が無効になるリスクがありますので注意が必要です。
退職勧奨を穏便に進めるために従業員への使え方を確認したい、退職勧奨に応じてくれない従業員を辞めさせたい、という場合には、まずはベリーベスト法律事務所 福岡オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています