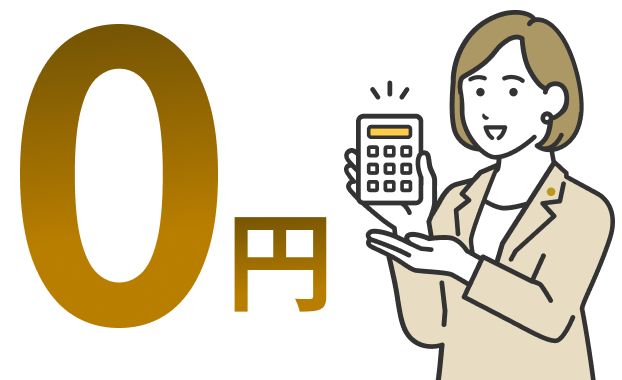特定財産承継遺言とは? 作成するメリットと注意点
- 遺言
- 特定財産承継遺言

裁判所が公表している司法統計によると、令和3年に福岡家庭裁判所に申し立てのあった遺言書の検認は、714件でした。法務局で保管されている自筆証書遺言および公正証書遺言は、検認が不要ですので、さらに多くの遺言に基づく相続が発生しているものと思われます。
特定の遺産を特定の相続人に相続させるために遺言を作成する方もいると思います。このような遺言を「特定財産承継遺言」といいますが、特定財産承継遺言を作成することによって、どのようなメリットがあるのでしょうか。また、遺言書を作成する場合には、無効にならないようにするためにいくつか注意するポイントがあります。
本コラムでは、特定財産承継遺言を作成するメリットとその注意点について、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、特定財産承継遺言とは
特定財産承継遺言とは、特定の遺産を1人の相続人または複数人に相続させる内容の遺言のことをいいます。たとえば、「土地Aを長男に相続させる」、「建物Bを二男に相続させる」といった内容の遺言です。
以前は、このような遺言のことを「相続させる旨の遺言」と呼んでいました。しかし、令和元年に施行された改正民法により、「特定財産承継遺言」という名称で呼ばれるようになりました。
2、特定財産承継遺言のメリット
特定財産承継遺言を作成することによって、以下のようなメリットがあります。
-
(1)遺産分割協議が不要になる
被相続人が死亡して相続が開始した場合、被相続人の遺産を分けるには相続人による遺産分割協議が必要になります。
しかし、特定財産承継遺言がある場合には、遺産分割手続きをすることなく、相続開始と同時に相続人に帰属することになります。そのため、特定財産承継遺言によってすべての遺産について誰が相続するのかを明確にしておけば遺産分割協議が不要になります。
遺産分割協議をしなければならないというのは、相続人にとっても負担になりますので、それを省略することができるのは、相続人にとって大きなメリットといえます。 -
(2)不動産の登記などの手続きがスムーズになる
遺産に不動産が含まれる場合には、特定財産承継遺言を作成することによって、登記手続きをスムーズに行うことができるというメリットがあります。
特定の財産を遺言で承継する方法には、特定財産承継遺言のほかにも特定遺贈という方法があります。しかし、特定遺贈によって不動産を承継した場合、受遺者は、他の相続人と共同で登記申請をしなければなりません。したがって、他の相続人の協力が得られなければ、スムーズに登記手続きを行うことができないのです。
これに対して、特定財産承継遺言では、遺言によって不動産を相続した相続人が単独で所有権移転登記手続きを行うことができます。他の相続人の協力は不要ですので、自分のペースで相続登記の手続きを進めることが可能です。 -
(3)相続トラブルを予防できる
遺言がない場合には、被相続人の遺産は、相続人による遺産分割協議を行い分割方法を決めなければなりません。しかし、遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員の同意が必要になります。そのため、相続人に行方不明の方や認知症の方がいる場合には、遺産分割協議を行うことができないという事態に陥ることがあるのです。このような場合、不在者財産管理人や後見人を選任することによって、遺産分割協議が可能になりますが、それには時間も手間もかかります。
また、遺産分割協議では話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停や審判で争うことになりますが、事案によっては解決までに長期間を要することも珍しくありません。
遺言書を作成すれば、このようなトラブルを予防することが可能です。将来相続人同士でトラブルになることを回避したいとお考えの方は、積極的に遺言書の作成を検討することをおすすめします。
3、特定財産承継遺言を作成する際の注意点
メリットばかりのように思えますが、特定財産承継遺言作成する際にも注意すべき点があります。
-
(1)相続人の遺留分に配慮する
特定財産承継遺言を作成する際には、法定相続人の遺留分にも配慮した内容にすることが必要です。
遺留分とは、相続人に保障されている最低限度の遺産の取得割合のことをいいます。遺留分を侵害する内容の遺言書でも、法律上は有効と扱われますが、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することにより、遺留分侵害額に相当する金銭を取り戻すことができます。遺留分権利者への支払いは金銭での支払いが原則となりますので、相続した遺産が不動産など簡単に売却できないものであった場合には、支払いに困ってしまう事態に陥りかねません。
相続争いを防止するために遺言書を作成したにもかかわらず、遺留分をめぐる争いが生じてしまっては元も子もないでしょう。そのため、遺言書を作成する際には、遺留分への配慮が必要になるのです。
もっとも、さまざまな事情から遺留分を侵害する内容での遺言を作成せざるを得ないこともあります。そのような場合には、付言事項を利用することによって、遺留分をめぐる争いを回避できる可能性もありますので、付言事項の利用も検討するようにしましょう。 -
(2)遺言の解釈をめぐってトラブルにならないようにする
特定財産承継遺言では、遺言書の書き方によっては、遺言の解釈をめぐってトラブルになる可能性もありますので注意が必要です。
たとえば、「土地Aを長男に相続させる」という遺言を残していた場合には、以下の3つの解釈が可能です。- ① 長男は土地Aだけを相続し、その他の遺産は他の相続人が相続する
- ② 土地Aを含む遺産を法定相続分で分割し、長男が土地Aを相続する
- ③ 土地Aを除く遺産を法定相続分で分割し、長男はそれに加えて土地Aを相続する
長男Aとしては、より多くの遺産をもらえる③の方法を主張することになりますが、他の相続人としては、①の方法を主張する可能性もあります。このように遺言の記載内容について、複数の解釈の余地が残されている方法は遺言として好ましいものではありません。
このような解釈をめぐるトラブルを防ぐためには、すべての相続財産を網羅した遺言にするのか、遺言に記載のない相続財産の分割方法を指定するなどの方法を検討する必要があります。 -
(3)形式面の不備によって無効にならないようにする
特定財産承継遺言による遺言書を作成する場合には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2つの方式が選択されます。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文を自筆で作成する方法の遺言です。遺言者のみで作成することができ、費用もかからないため非常に手軽な作成方法ですが、形式面の不備によって遺言が無効になるリスクがある点に注意が必要です。
これに対して、公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成する遺言です。2人以上の証人が必要になり、作成手数料がかかるなどのデメリットがありますが、専門家である公証人が作成するため形式面の不備によって遺言が無効になるリスクはほとんどありません。
遺言の内容を実現するためには、有効な遺言でなければなりませんので、無効になるリスクを少しでも減らしたいとお考えであれば、公正証書遺言での作成を検討してください。ただし、公証役場の公証人は、遺言の内容について詳しいアドバイスをしてくれるわけではない点に注意が必要です。
4、特定財産承継遺言の作成を弁護士に依頼するべき理由
特定財産承継遺言の作成は、弁護士に依頼することをおすすめします。
-
(1)トラブルが起こらないよう考慮した内容を提案してもらえる
特定財産承継遺言を作成する際には、相続人の遺留分に配慮し、複数の解釈の余地を残さないような内容にしなければなりません。このような遺言を作成するには、遺産相続に関する知識や経験が不可欠となります。
弁護士であれば将来起こる可能性があるトラブルを予測し、それに対応することができる遺言書の内容を提案することができます。また、弁護士に依頼をすれば、遺言の形式や内容の不備によって、遺言が無効になってしまうリスクも回避することができます。
公正証書遺言の形式にしたとしても、前述の通り、公証人は遺言内容についてのアドバイスをしてくれませんので、希望する内容の遺言を作成するためにも、遺言の作成は、専門家である弁護士にお任せください。 -
(2)遺言の執行まで依頼できる
遺言を作成したとしても、遺言者が亡くなった後では、遺言の内容どおりに相続が実現されたのかがわかりません。また、遺言の内容を実現するにあたっては、専門的な知識が必要になりますので、遺言の執行を相続人に任せるのにも不安があるでしょう。
そのような場合には、遺言執行についても弁護士にお任せください。遺言書に遺言執行者として弁護士を指定しておくことによって、遺言者の死後、弁護士が遺言の内容を確実に実現することができます。遺言書の作成を依頼した弁護士に遺言執行者も依頼することができますので、ご希望の方は、遺言作成を依頼した弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。
5、まとめ
特定財産承継遺言を作成することによって、将来の相続トラブルを回避し、相続人の負担を軽減することができるといったメリットがあります。ただし、遺言には、厳格な要件が定められていますので、不慣れな方では形式面や内容面の不備によって遺言が無効になってしまうリスクがあります。
そのようなリスクを回避するためには弁護士のサポートが必要不可欠です。遺言書の作成をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスまでお気軽にご相談ください。必要に応じて相続税などについても考慮し、傘下の税理士法人などとも連携を取りながら対応することが可能です。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています